診療案内
course
実は耳や鼻だけでなく、「舌の痛み」も耳鼻咽喉科の診療領域です。
「舌が痛い」症状で考えられる原因は、細菌や真菌(カビ)による炎症、義歯や銀歯などの被せ物による刺激や歯科金属アレルギー、口の中の乾燥、がんなど腫瘍、貧血や亜鉛・ビタミン不足、薬の副作用、長期間の喫煙、神経痛など様々です。
さらに、「舌痛症(ぜっつうしょう)」と呼ばれる、舌には異常がないのに、舌の痛みがある場合もあります。舌の痛みは、原因を見つけて適切に対処すれば、薬物療法などで改善するケースも多くなっています。
舌の痛みでお困りの方や「口内炎」が2週間以上続いている方は、当院までお気軽にご相談ください。
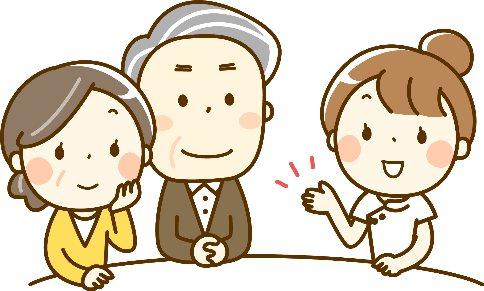
「舌が痛い」場合に考えられる原因とは?
外傷性
うっかり舌を噛む、義歯や被せ物が合っていないなどで舌が傷つき、痛みを感じます。
誤って噛んでしまった場合には、様子見していても1週間程度で治りますが、義歯や被せ物については、かかりつけの歯科医院で調整してもらうと良いでしょう。
細菌や真菌感染による炎症(舌炎)
- 口腔カンジダ症
舌に白い苔のようものが付着しますが、ガーゼなどで拭うとすぐ取れます。口の中に元々あるカンジダ菌(カビの一種)が原因です。
高齢者、がん・感染症などで免疫力が低下している時に現れやすくなっています。 - 単純性ヘルペス感染
発熱や倦怠感を伴い、多数の口内炎ができます。子どもの感染が多いですが、大人に見られます。 - 水痘、帯状疱疹ウイルス感染
幼少時に感染し体内に残存していた水痘・帯状疱疹ウイルスが、大人になってから体調不良時に活性化することで、帯状の赤みと発疹が片側だけ現れます。強い痛みが特徴です。 - アフタ性口内炎
赤くふちどられた白い潰瘍が特徴で、ストレス、睡眠不足、ビタミン不足など体調不良時によくみられる「口内炎」です。通常1~2週間で自然に治ります。 - 天疱瘡(てんぽうそう)
水疱ができますが、すぐ破れて出血しやすいびらん(部分的に荒れている状態)ができるのが特徴で、痛みで食事などに支障を来します。自己免疫疾患で国の難病指定となっています。

口の中の乾燥
唾液の分泌量が減る要因には、薬(抗ヒスタミン薬、降圧剤、向精神薬など)の副作用、咽頭がんなどの放射線治療後、全身疾患(糖尿病、シェーグレン症候群など)があります。
悪性腫瘍
均一でない白斑や腫瘍が見られ、知覚神経を刺激します。
全身疾患の2次的症状
鉄、亜鉛、ビタミンなどが欠乏すると、舌の乳頭(つぶつぶした細い突起)がなくなり、舌の表面が滑らかになります。鉄不足の場合には、舌表面が赤くなり、嚥下障害(飲み込みづらい)も一緒に起こります。過去に貧血を指摘された方、胃の手術後、菜食主義の方などに見られます。
神経痛
舌にある神経が隣り合った血管などに圧迫されることで痛みが片側にだけ現れます。
舌を動かす動作で舌の前の方に鋭い痛みを感じる「三叉(さんさ)神経痛」、舌の付け根部分に鋭い痛みを感じる「舌咽(ぜついん)神経痛」があります。薬物療法のほか、手術が必要となる場合もあります。
舌痛症
局所所見や検査所見で舌に異常が見当たらないのに、やけどのようなヒリヒリ感、ピリピリとしびれるような痛みを感じます。
食事をしたり、人と会話したりしているときには、痛みが軽くなる特徴があります。
40歳以降の閉経前後の女性が多く、ホルモンバランスや自律神経の乱れなど心因性との関連も報告されています。
「舌が痛い」場合の検査

舌の痛みには、がんなど重大な病気が隠れていることもあります。
問診や様々な検査を組み合わせて、痛みの原因を調べます。
問診・視診・触診
どのような時に痛みが強くなるのか、軽くなることはあるのか、いつ発症時期したか、などについてお伺いします。また、炎症や腫瘍など舌粘膜の変化の有無を視診・触診でじっくり調べます。
細菌培養検査
綿棒で舌をこすって、細菌やウイルスに感染しているかどうかを調べます。
検査結果が出るまで1週間程度かかりますが、適切な治療薬を選択するために有効です。
場合によっては、局部麻酔の上、組織検査(生検)も行います。
唾液量の検査
ガムまたはガーゼを数分間噛んで、唾液の分泌量を測定します。
特に女性は、加齢に伴い唾液の分泌量が減少しますが、全身疾患である「シェーグレン症候群」や口腔内への放射線治療、高血圧の薬の副作用でも口の中の乾燥が見られます。
血液検査
見た目上、舌に異常が見られない場合は、血液検査を行います。
貧血(鉄)や亜鉛、ビタミンなどの欠乏や自己免疫について、調べます。
そのほか、神経痛が疑われる場合にはMRI検査、しこりや腫瘍がある場合には組織検査(生検)を行うことがあります。
必要に応じて、対応病院をご紹介します。
「舌が痛い」場合の治療法

薬物療法
舌粘膜に異常が見られる場合には、うがい薬で消毒を行い、軟膏(ステロイド剤、抗ウイルス剤、抗真菌剤など)で炎症を抑えます。
貧血や亜鉛・ビタミン不足の場合には内服薬で補充し、神経痛の場合には、抗てんかん薬を使用します。口腔乾燥症など症状によっては、漢方薬が有効なケースもあります。
舌痛症の場合には、原因不明の場合も多く、薬による対症療法を行っても改善しない場合には、心理療法も組み合わせて行います。
薬の変更や中止
高血圧や糖尿病などの薬の副作用が原因であることが明らかな場合には、医師と相談して、薬を減らしたり、変更したり、場合によっては中止など見直しを行います。
外科的手術
神経痛が原因となっている場合、薬物療法のほかに脳に繋がっている神経と圧迫している血管を剥がす手術(神経血管減圧術)を行うことがあります。
必要に応じて、対応病院をご紹介します。
よくあるご質問

1)舌の痛みがあるとき、日常生活での注意点はありますか?
一般的に過労やストレスがあるような体調不良時は、細菌やウイルス感染を起こしやすいので、十分な栄養と休養をとって、生活のリズムを整えましょう。
また、舌粘膜を傷つけないように、過剰な歯磨きや刺激物の摂取を控えることや喫煙している場合には禁煙をして、口の中を清潔にしておくことも大切です。
2)舌の痛みですぐに病院に行った方が良い場合は、どんなケースですか?
舌の痛みのほか、舌に拭っても取れない白い病変が現れる「白板症(はくばんしょう)」や鮮やかな赤色をした滑らかなビロード状の病変「紅板症(こうばんしょう)」が見られる場合には、速やかに耳鼻咽喉科で専門医による診察を受けましょう。
これらは悪性化する可能性が高いため、手術で切除したほうがよい“前がん病変”と呼ばれています。
まとめ

舌には食べ物を噛む(咀嚼:そしゃく)、飲み込む(嚥下:えんげ)、声を出す(発声)といった役割だけでなく、味覚を感じたり、食べ物を選別したりする働きもあるため、「舌が痛い」と、何をしても気になってしまいますよね。
さらに、痛みが続く場合「がんかも?」と不安になることで、余計に痛みが増すケースもあり、舌の痛みは“QOL(生活の質)の低下”に直結します。
当院は「耳鼻咽喉科専門医」として、痛みの原因を丁寧に調べて適切な治療に繋げることで、速やかに痛みが改善できるよう努めています。
舌の痛みで気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

